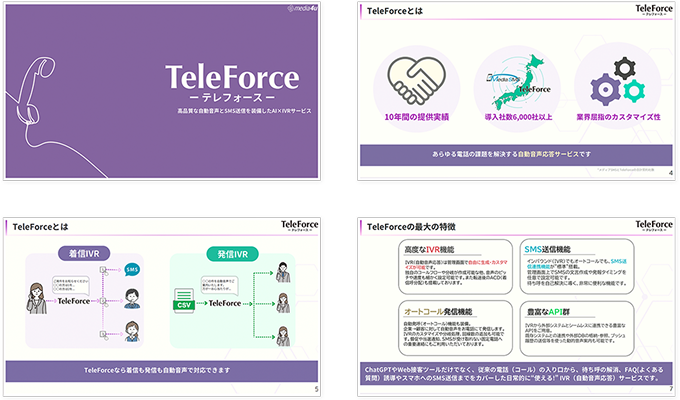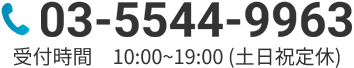あふれ呼とは?
あふれ呼とは、コールセンターやサポートセンター、企業、店舗、クリニックなど着信数が多い場合に発生する「対応できない呼び出し(コール)」のことを指します。増え続ける顧客からの問い合わせに迅速に対応することは、顧客満足度の向上に欠かせません。本記事では、あふれ呼の基本的な仕組みや、効果的な対応方法、さらには成功事例について詳しく解説します。

あふれ呼とは?基本の仕組みと役割
あふれ呼の定義
「あふれ呼」は、企業が対応可能な呼量を超えた際に発生する未応答の通話を指します。電話窓口やコールセンターの運営において発生しやすい現象で、顧客との信頼関係に直接影響を与えます。
背景にある業界動向
問い合わせ急増の背景
プロモーションや災害時の特定情報への需要増加が一因。
企業のリソース不足
人員やシステムが繁忙期に対応しきれないケースが多い。
顧客の即時性への期待
デジタル時代では、顧客は迅速な対応を期待する傾向が強まっています。
あふれ呼の発生原因
内的要因
スタッフ不足
コールセンターのオペレーター人数が需要に対して不十分。
予測の不正確さ
繁忙期の需要を正確に予測できないため、適切なリソース配分が困難。
外的要因
突発的なイベント
災害やキャンペーンなど、特定の出来事で急激に呼量が増加。
競争環境の変化
顧客が他社と比較しやすくなったことで、対応の速さが評価基準に。
あふれ呼が発生する原因とビジネスへの影響
あふれ呼が発生する要因にはいくつかのものがあります。ここでは、主な原因とビジネスへの影響を解説します。
主な原因
問い合わせ数の急増
繁忙期や特定のキャンペーン期間などに、通常の問い合わせ数が増加するとオペレーターが対応しきれず、あふれ呼が発生します。
人員不足やシフト管理の不備
オペレーターが不足していたり、シフトの管理が適切でない場合、ピーク時に対応できずあふれ呼が発生します。
システム障害やトラブル
サービスの障害やトラブルが発生した際、同じ内容の問い合わせが一度に集中することが原因で発生することもあります。
複雑な問い合わせ対応
対応時間が長くなるような複雑な問い合わせが増えると、他の顧客対応が後回しになり、あふれ呼が発生するリスクが高まります。
ビジネスへの影響
顧客満足度の低下
長い待ち時間やつながらない電話により、顧客が不満を感じることが増え、顧客満足度の低下につながります。
顧客離れのリスク
特にサポートが重要な業界では、あふれ呼の発生が顧客離れの要因になります。別のサポートが手厚いサービスに移行することも考えられます。
ブランドイメージの低下
サポート対応が悪いという印象が広まると、ブランドイメージの低下にもつながります。
従業員の負担増加
あふれ呼が多発するとオペレーターへの負担が大きくなり、ストレスが増加し、離職率の上昇を招くことがあります。
あふれ呼への効果的な対応方法
あふれ呼を防ぐためには、事前に対策を講じ、柔軟な対応が求められます。以下は、効果的な対応方法の例です。
1. AIチャットボットの導入
チャットボットを活用することで、FAQなど簡単な問い合わせを自動化し、オペレーターの負担を軽減できます。これにより、オペレーターは複雑な問い合わせに集中することが可能です。ある企業では、チャットボットの導入により、問い合わせ件数の29%を自動対応化しました。
2. コールバック機能の提供
顧客が待機する代わりに、後でオペレーターから電話をかけ直す「コールバック機能」を提供することで、待ち時間のストレスを軽減できます。特に、急ぎではない問い合わせについては、顧客にとっても便利です。
3. 業務時間外の問い合わせ対応
営業時間外でもAI音声案内や簡易的なサポートを提供することで、翌営業日の問い合わせ件数を減らすことが可能です。24時間対応の体制を整えることができれば、あふれ呼のリスクを大幅に軽減できます。
4. 人員配置の最適化
問い合わせのピーク時間を把握し、シフトを最適化することで、あふれ呼の発生を抑えることができます。通話データを分析し、どの時間帯に問い合わせが集中するかを把握することで、効率的な人員配置が可能です。
5. IVRなどの自動振り分けの活用
あふれ呼対応では、自動音声応答(IVR)や問い合わせ内容に応じた自動振り分けが効果的です。たとえば、請求に関する問い合わせや商品の返品・交換については、個別の短縮番号を提供することで対応速度が向上します。また、問い合わせ内容に応じて自動で担当部署(担当者)へ自動転送することで取次の手間が減り、ガイダンス内で回答、SMS配信など転送しない導線を作ることで有人対応が必要な案件を漏らさず対応することができるようになります。
この記事を読んだ人にオススメ
自動音声応答(IVR)については下記記事で詳しく解説しています。
【初心者向け】IVR(自動音声応答)とは?基本機能とメリットを解説
あふれ呼対応の成功事例
あふれ呼対策として成功を収めた事例を紹介します。
1. 小売業界の事例 – チャットボット導入による対応効率化
導入前の課題
商品に関する問い合わせが増加し、あふれ呼が頻発。
導入後の効果
AIチャットボットを導入し、よくある質問に対応した結果、あふれ呼の件数が24%削減。オペレーターが他の複雑な問い合わせに集中できるようになり、顧客対応の質も向上。
2.オフィスの事例 – IVRの活用
導入前の課題
部署が複数あり電話の取次が8割発生し、電話対応者に負荷がかかっていた。
導入後の効果
IVRを導入することで、取次の手間を削減。また、営業時間の確認などよくある質問はガイダンスで回答、LPやサイトのリンクをSMS送信した結果、有人対応の問い合わせ数が削減し業務効率化を図ることができた。
3. 通信業界の事例 – コールバック機能の活用
導入前の課題
契約内容の確認やプラン変更の問い合わせが多く、顧客が長時間待たされるケースが増加。
導入後の効果
コールバック機能を導入し、顧客に適切な時間に折り返し対応した結果、顧客満足度が21%向上、待ち時間への不満が大幅に減少。
4. 金融業界の事例 – ピーク時間の人員最適化
導入前の課題
お客様からの問い合わせ数が多く、顧客満足度が低下。
導入後の効果
通話データを分析し、ピーク時間に人員を増加した結果、ピーク時の対応件数が16%増加し、顧客満足度も向上。また、短縮ダイヤルを導入することで、特定の問い合わせ対応の効率も向上。
5. IT業界の事例 – FAQシステムの整備
導入前の課題
製品サポートに関する問い合わせが多発。
導入後の効果
FAQシステムを整備し、顧客が自己解決できる環境を整えた結果、あふれ呼が21%減少。問い合わせが簡素化され、オペレーターの対応負担が軽減。
まとめ
あふれ呼は、コールセンターやサポートセンターの運営において顧客満足度や効率に大きな影響を与える要因です。AIチャットボット、IVR導入、コールバック機能の活用、人員配置の最適化など、適切な対応策を取ることで、あふれ呼を抑え、顧客満足度の向上につなげることができます。ビジネスの成長に合わせたあふれ呼対策を行い、顧客との関係をさらに強化しましょう。
「あふれ呼」を解決したい方へ。課題に沿って最適な解決方法を提案しますので、お気軽にお問合せください。