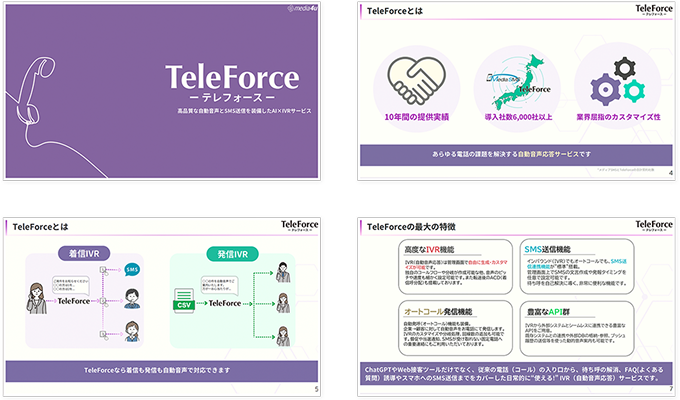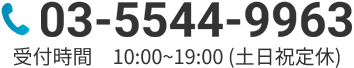待ち呼とは?
待ち呼は、コールセンターで顧客が電話応答を待っている状態を指し、長時間の待ち時間は顧客満足度に大きな影響を与えます。待ち呼を効果的に減らすための対策を取ることは、ビジネス成長にもつながります。本記事では、待ち呼の基本的な仕組みや原因、解消するための方法、さらに成功事例までを詳しく解説します。

待ち呼とは?基本の仕組みと役割
待ち呼の基本定義と具体例
待ち呼(まちこ)とは、電話をかけた際にオペレーターが対応するまでの間、顧客が待機している状態を指します。特に、コールセンターやカスタマーサポート業務において問題視される現象です。以下は具体例です。
具体例1: コールセンターでの待ち呼
繁忙期に電話をかけた際、「現在の待ち時間は約5分です」というアナウンスが流れる状態。
具体例2: サポートデスクでの待ち呼
トラブル発生時、サポート窓口に電話をかけたが、オペレーターが対応できるまで15分以上待たされるケース。
「あふれ呼」との違い
「あふれ呼」とは、顧客からの電話が集中したことでコールセンターの電話回線数を上回り、対応できずに「あふれてしまった呼(コールセンターへの着信)」を表す用語です。
この記事を読んだ人にオススメ
この記事を読んだ人は以下の記事も読んでいます。
あふれ呼とは?基礎知識と対策方法
待ち呼が発生する主な原因
待ち呼が発生する背景には、いくつかの要因があります。ここでは、主な原因について詳しく解説します。
1. 問い合わせ件数の急増
待ち呼が発生する大きな原因のひとつは、短期間での問い合わせ件数の増加です。例えば、キャンペーン期間中や新商品の発売後など、特定の時期に問い合わせが集中しやすく、オペレーターが対応しきれずに待ち呼が発生します。
2. オペレーターの不足
オペレーターの数が不足している場合、問い合わせが集中すると待ち呼が発生しやすくなります。特に、予測が難しいピーク時には、適切な人員配置がされていないと待ち呼が増加します。
3. 長時間の応対が必要なケース
問い合わせ内容が複雑で応対時間が長引く場合、待ち呼が発生しやすくなります。たとえば、クレーム対応や契約変更といった時間がかかる業務では、待ち時間が長くなる傾向にあります。
4. システムのトラブルや遅延
システムの不具合や遅延が発生した場合、オペレーターが迅速に対応できず、待ち呼が増加する原因となります。特に、システムのダウンタイムが長引くと、顧客対応に大きな影響が出ます。
待ち呼の影響を徹底分析
待ち呼が顧客に与える影響
顧客体験の低下
待ち時間が長いと、顧客は「自分が重要視されていない」と感じ、企業への信頼感を失います。
クレームや不満の増加
「待たされた」という理由で、問い合わせ対応後もクレームが増加しやすくなります。
他社への乗り換えリスク
調査によると、待ち時間が2分を超えると、20%以上の顧客が他社への乗り換えを検討します。
待ち呼が企業に与える影響
ブランドイメージの低下
「つながらない窓口」の印象は、口コミやSNSで広まり、企業全体の評価を下げるリスクがあります。
効率性の悪化によるコスト増加
待ち呼が増えることで対応が後手に回り、リソースを無駄に消費するケースが増加します。
待ち呼を減らすための効果的な対応方法
待ち呼の発生を抑えるためには、さまざまな対策が必要です。以下は、効果的な対応方法の例です。
1. IVR(自動音声応答)の活用
IVRシステムを導入し、問い合わせ内容に応じた自動振り分けを行うことで、オペレーターの負担を軽減し、待ち呼を減らすことができます。たとえば、「1:商品に関する問い合わせ」「2:請求に関する問い合わせ」など、簡単な操作で適切な部門に接続する仕組みを作ることで、顧客の待機時間を短縮できます。
この記事を読んだ人にオススメ
IVRについてはこちらの記事でも解説しています。
【初心者向け】IVR(自動音声応答)とは?基本機能とメリットを解説
2. コールバック機能の提供
待機中の顧客にコールバック機能を提供することで、顧客が待ち時間のストレスを感じることなく対応を受けられます。特に、すぐに対応が必要ない問い合わせに対しては、顧客が待機する代わりに後から対応することで待ち呼を分散できます。
3. チャットボットやFAQシステムの活用
AIチャットボットやFAQシステムを導入することで、よくある質問に対して自動応答が可能となり、問い合わせ件数を減らすことができます。例えば、営業時間や商品の基本情報といった一般的な質問は自動応答で対応し、オペレーターが複雑な問い合わせに集中できる環境を作りましょう。また、FAQのURLをSMSで自動送信することで、24h対応が可能になります。
4. オペレーターのシフト管理と柔軟な人員配置
通話データを分析し、問い合わせのピーク時間帯を把握することで、シフトを最適化することが可能です。たとえば、週末や特定の時間帯に問い合わせが集中する場合、オペレーターを増やして対応することで待ち呼の発生を抑えられます。
5. 効率的なオペレーター教育
オペレーターが迅速かつ的確に対応できるように教育を充実させることも、待ち呼の削減に効果的です。特に、初回対応で問題を解決する能力を向上させることで、対応時間の短縮が図れます。例えば、商品知識や電話対応スキルを高める研修を行うことで、応対効率が向上し、待ち呼の削減につながります。
待ち呼対策の成功事例
待ち呼対策として効果的な事例を4つ紹介します。
1. 小売業界の事例 – 自動応答システムによる待ち呼削減
導入前の課題
商品に関する問い合わせが急増し、待ち呼が頻発。
導入後の効果
IVRとチャットボットを導入し、よくある問い合わせの58%を自動化することでオペレーターの対応負担を軽減。待ち呼が37%減少し、顧客満足度が16%向上。
2. 医療業界の事例 – コールバック機能の活用
導入前の課題
予約や診療に関する問い合わせが集中し、待ち呼が発生。
導入後の効果
コールバック機能を導入し、オペレーターが対応可能な時間に電話をかけ直すシステムを導入。顧客が待機する時間が削減され、待ち呼が30%減少。また、患者満足度が向上し、リピート率も増加。
3. 通信業界の事例 – FAQシステムの整備とチャットボットの導入
導入前の課題
全ての問い合わせをオペレーターが対応する運用の為お客様への案内に時間がかかると待ち呼が発生。
導入後の効果
FAQシステムとAIチャットボットを整備し、問い合わせのうち39%が自動対応できるようになり、オペレーターの負担が軽減。複雑な問い合わせはオペレーターが対応する体制を整えた結果、待ち呼が25%減少し、顧客満足度が11%向上。
4. 金融業界の事例 – ピーク時間のシフト最適化
導入前の課題
プラン変更、登録情報の変更など問い合わせや質問が増えるタイミングで、待ち呼が発生。
導入後の効果
通話データを分析し、平日夜間に問い合わせが集中する傾向を把握。夜間にオペレーターを増員し、待ち呼が15%減少。これにより、対応スピードが向上し、顧客からの評価もあがった。
まとめ
「待ち呼」は、多くの企業に共通する課題ですが、適切なIVRの導入により解決可能です。顧客満足度の向上、業務効率化、コスト削減を実現し、競争力を強化するチャンスを逃さないようにしましょう。
今すぐIVR導入を検討し、待ち呼をゼロに!